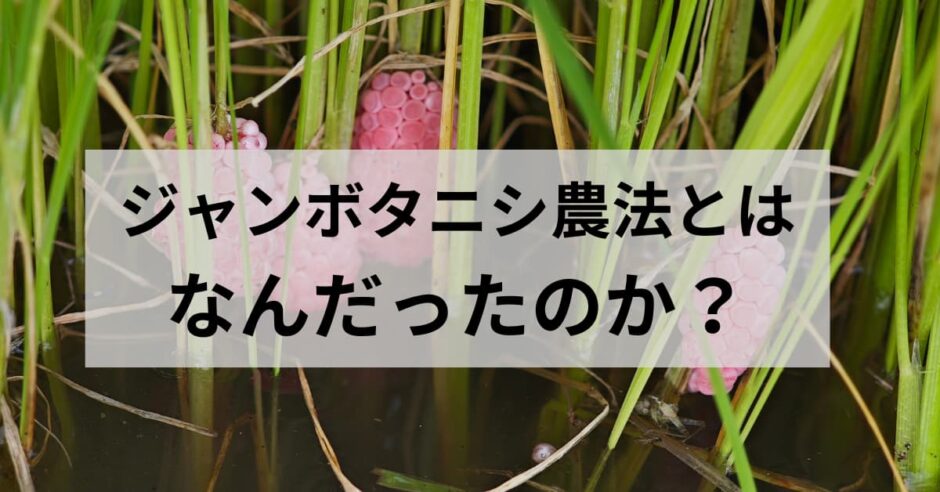参政党のSNS投稿をきっかけに注目を集めた「ジャンボタニシ農法」。雑草を食べさせて除草する農法ですが、ジャンボタニシはすぐ地域全体に広がり稲を食害するため、今いない所に放すことは非常に危険です。本記事では、ジャンボタニシの生態や特徴、卵や生体の駆除方法、対策や天敵について詳しく解説します。
参政党発のジャンボタニシ騒動とはなんだったか
2024年初頭、参政党の一部の支部や党員がSNS上で「ジャンボタニシ農法」を推奨する投稿をおこない、物議を醸しました。
ジャンボタニシは稲を食い荒らす外来種。一度広まると根絶困難で、ジャンボタニシを放す様子や、「ジャンボタニシ農法を全国でやったらいい(参政党員)」などの的はずれな発言が批判を浴びました。
さらに「地域ぐるみで40年上やっています(参政党員)」などの事実と異なる発言もあり、該当JAが否定したり、農林水産省が注意喚起のTweetをする事態となっています。
- 「ジャンボタニシ農法を全国でやったらいい(参政党員)」
→農林水産省から新たに放飼しないよう注意喚起される - 「我が家は40年以上ジャンボタニシ活用して無農薬米作ってる(参政党員)」
→今から40年前の1980年代はジャンボタニシが日本に入ってきた頃で、ジャンボタニシ農法はまだない。該当エリアで試されるようになったのは2000年ごろ。 - 「地域ぐるみでJA福岡市が指導しました(参政党員)」
→該当JAから完全否定される。「ジャンボタニシを除草のために水田に放つことや、ジャンボタニシを活用した除草を推奨している事実は一切ございません」
あまりの炎上に参政党は党としては推奨していないと軌道修正しましたが、反ワクチンやオーガニック・無農薬志向からの農薬批判など、非科学的な主張を繰り返してきたため、今後も要注意と言えるでしょう。
参政党のジャンボタニシ騒動に関する各種報道
SNSでの炎上に引き続き、全国ニュースでも報道される事態となりました。
- ジャンボタニシの放し飼い、除草目的でも「やめて!」と農水省。「一度侵入・まん延すると根絶は困難」 | ハフポスト NEWS
- ジャンボタニシで除草? 投稿が炎上 農水省が注意喚起 米農家「信じられない」(テレ朝)
- 「気持ち悪いんです、これ」 農水相、ジャンボタニシの放し飼いで注意喚起 イネに被害 – 産経ニュース
- ジャンボタニシ放飼「止めて!」農水省が警鐘 X論争で…飛び火のJA福岡市も訴え「推奨している事実一切ない」: J-CAST ニュース
除草目的の「ジャンボタニシ農法」とは?


話題の「ジャンボタニシ農法」ですが、実在する農法ではあります。ジャンボタニシの習性を利用して、水田の除草をおこないます。
「ジャンボタニシで無農薬農法!」と持て囃す向きもありますが、ジャンボタニシが蔓延してもう根絶できない地域で、なんとか活用できないかという苦肉の策であることに注意が必要です。
ジャンボタニシ農法を紹介しているサイトでも、ジャンボタニシがいない地域に新たに放すな、と注意書きが入っているのが普通です。
ジャンボタニシに雑草だけ食べさせる方法
ジャンボタニシは稲を食害するのに、どうやって雑草だけ食べさせるのか。それは、餌を食べるのは水面下だけという習性を利用するからです。
- ジャンボタニシは、稲も雑草も区別せず食べる(大前提)
- 田植え直後の苗は倒れたり水面下に芽があって食べられやすい
というわけでジャンボタニシの食害が発生します。
イクラのようなジャンボタニシの卵は有名ですが、実は餌を食べるのは水面下だけなんですね。そこで、田植え直後は水深を1cm等に低くして、苗を食べられないようにするのがジャンボタニシ農法です。稲が育った後に水位をあげれば、雑草だけ食べてくれるという仕組み。
- ジャンボタニシは、水面下で餌を食べる
- ジャンボタニシは、水上に登って産卵するが、登っては食べない
ジャンボタニシ農法の手順
以上をまとめると、ジャンボタニシ農法とは苗を植えた後の水位を調整することで、食害対象をコントロールする農法であることがわかります。
- 苗を植える
- 水深を1cm等に低くする。
- 苗の葉は水上にあるので食べられない
- 稲が十分育った後水位を上げると、雑草だけが食べられる
ジャンボタニシ農法は持て囃すものではない
これだけ覚えて帰って欲しいのですが、ジャンボタニシ農法をやりたいからジャンボタニシを放す、これはNGです。まして、新規就農する人がやることではありません。
なぜか。ジャンボタニシがいないところに新たに放流すると、水路をつたって地域全体に広がります。当然、周りの農家さんは大激怒です。農薬を減らしたい、自然農法がよい、その理想は結構ですが、自分の田んぼだけで済まないことを意識する必要があります。
また、cm単位の繊細な水位管理が必要で、失敗したら全滅もあり得ることを考えると、リスクが高すぎます。毎年ジャンボタニシに悩んでいて、その習性を活用しようという人がやるもので、経験が少ない人がやるものではありません。
ジャンボタニシの特徴


ジャンボタニシは、南米原産の外来種であり、日本の水田や水路に深刻な影響を与えることで知られています。ここでは、ジャンボタニシの生態や習性、生息域や天敵について解説します。
ジャンボタニシの生態と習性
ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は、主に水中で生活する淡水巻貝です。南米原産で、1981年に食用目的で台湾から日本に持ち込まれました。全国500箇所も養殖所が設けられましたがその後放棄され、野生化しました。水田や水路、池などの淡水域に生息し、温暖な気候を好みます。
食性は雑食で、芽などのやわらかい植物を好みます。そのため、稲の苗が食害にあい、世界の侵略的外来種ワースト100、日本の侵略的外来種ワースト100などに選ばれています。
ジャンボタニシは旺盛に繁殖します。年数回産卵し、夜間に水際の植物の茎やコンクリ壁に登って卵を産み付けます。ピンク色の卵が集まった卵塊は2週程度で孵化し、幼貝は2ヶ月ほどで繁殖力を持ちます。
- 淡水生の巻貝類の多くがコケや水底の沈殿物等を主食とするのに対し、本貝は水草そのものを摂食することが特徴
- 水中にあるものしか食べることができず、若い稲の葉は水中に引き込んで食害する。
ジャンボタニシの生息域
ジャンボタニシは南米原産だけあって、冬季の死亡率は高いものがあります。14度以下では活動を停止し土中などで越冬しますが、暖冬や温暖化により個体数が増えたり、生息域が北上する傾向にあります。
沖縄・九州・中国・四国の他、温暖な太平洋側を中心に生息し、現在の前線は滋賀県や関東にあるようです。
ジャンボタニシの卵には毒があるって本当?
ジャンボタニシの卵には神経毒があるとされ、ピンク色の目立つ卵塊でありながら、食べる生き物はほとんどいないとされています。しかし、人間がこの毒を過剰に恐れる必要はありません。触った後は、手を洗う程度で十分です。
卵塊は水中に落とすと死にますが、孵化直前の白い卵は孵化してしまうので、物理的に潰した方がよいでしょう。


ジャンボタニシの天敵は?
ジャンボタニシの卵塊は食べる生き物がいませんが、孵化した後の幼貝は鳥や魚、甲殻類など多くの生き物に食べられています。たとえば、アイガモやコイ、ザリガニ、クサガメ、ドブネズミなどが天敵として挙げられています。
しかし、水田にはジャンボタニシの天敵が少ないため、繁殖して増えてしまうという事情があるようです。
河川や池に普通に生息している多くの魚や甲殻類、カメなどはスクミリンゴガイの天敵です。私たちが試験した在来または帰化した46種の生物のうち、27種がスクミリンゴガイ(孵化貝)を捕食しました。
九州沖縄農業研究センター:スクミリンゴガイ | 農研機構
ジャンボタニシ対策の難しさ
ジャンボタニシの駆除は非常に困難。一度繁殖すると根絶が難しく、化学薬品や物理的手段による長期的な管理が必要になってきます。
- 水路からの侵入防止(金網やネット設置)
- トラップによる誘引・捕獲
- 水路での殺卵
- 石灰窒素散布・薬剤配布
- 冬期の耕うん(物理破壊&寒さにさらす)
- 水路の泥上げ
ジャンボタニシやジャンボタニシ農法に関するFAQ
- ジャンボタニシはいつどうやって日本に入ってきたの?
- ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は1981年に食用目的で台湾から日本に導入されました。その後、各地の養殖場が廃れるとともに野生化しました。
- ジャンボタニシ農法とは?
- ジャンボタニシ農法とは、草を食べる性質を利用して除草目的でジャンボタニシを使う農法です。ただし、今いない地域に新たに放つことは、地域の稲作を破壊し、世間の大きな非難を浴びることになるでしょう。
- タニシとジャンボタニシの見分け方は?
- 大きさからの判断は難しく、オオタニシなど在来種が間違って駆除される例も見かけます。卵塊の有無で生息を判断したほうが簡単です。ジャンボタニシは1段目の殻が極端に大きく、2段目以降極端に小さくなる殻の形から判別可能です。
- ジャンボタニシの卵には毒があるって本当?
- 本当ですが、触れた後の手を洗う程度で十分です。人間の被害事例は聞いたことがありません。
- ジャンボタニシの卵は水に落とすと良いって本当?
- 本当です。ただし、白い卵は孵化直前なので物理的に潰した方がよいとされています。
- ジャンボタニシには寄生虫がいるって本当?
- 本当です。ジャンボタニシには寄生虫(広東住血線虫)がいます。生あるいは加熱不十分で食べると体内に入るので、手袋をして触ったり、火を通してから食べるようにしましょう。
まとめ
ジャンボタニシ農法は、ジャンボタニシの雑草食性を活用した除草方法ですが、稲への被害や外来種としてのリスクが高く、積極的に各地へ広げるような農法ではありません。南米原産のジャンボタニシは、温暖な気候を好む淡水巻貝で、雑草や稲の若苗を食べます。繁殖力が強く、ピンク色の卵を産み付け、天敵には鳥や魚、カメなどがいます。駆除には化学薬品や物理的手段が必要で、一端侵入すると根絶は困難です。